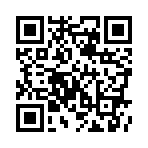2012年12月22日
今、どうなってるの?8
今度の選挙で、自民党が大勝し、
これによって日銀法を改正して、
年2パーセントの物価上昇を目標にする
という考えが現実的になってきました。
いいことですね。ただ、本当に出来るのかと
いう不安があります。はたして、安部内閣で
このようなことが可能なのかと
多くの人が懸念を抱いているのだと思います。
ひたすら、安部内閣にがんばってもらうほかありません。
先日、大阪の橋本さんが「政治は実行力だ。
その実行力が乗数になると考えるといい」というのです。
ようするに、もしいいアイディアが10個あり、
これに実行力をかけると、
どれだけ実行されるかわかるというのです。
すなわち、10のアイディア×実行力・・・
もし、実行力が0.1なら、
10のうち1しか実行できない。
もし、実行力が0.5なら、
5個実行される。もし、アイディアが5個しかなくても、
もし、実行力が1あれば、5個のことが実行されるというのです。
この考えは納得いくものではありませんか。
これによって日銀法を改正して、
年2パーセントの物価上昇を目標にする
という考えが現実的になってきました。
いいことですね。ただ、本当に出来るのかと
いう不安があります。はたして、安部内閣で
このようなことが可能なのかと
多くの人が懸念を抱いているのだと思います。
ひたすら、安部内閣にがんばってもらうほかありません。
先日、大阪の橋本さんが「政治は実行力だ。
その実行力が乗数になると考えるといい」というのです。
ようするに、もしいいアイディアが10個あり、
これに実行力をかけると、
どれだけ実行されるかわかるというのです。
すなわち、10のアイディア×実行力・・・
もし、実行力が0.1なら、
10のうち1しか実行できない。
もし、実行力が0.5なら、
5個実行される。もし、アイディアが5個しかなくても、
もし、実行力が1あれば、5個のことが実行されるというのです。
この考えは納得いくものではありませんか。
2012年12月22日
Who am I? 26
Who am I? 26
A lot of old heroes from China had me
which was exaggerately said to be 3,000 feet long.
So did Abraham Lincoln and Santa Clause.
Some people call “Soup catcher” or “Flavor Saver”.
A lot of old heroes from China had me
which was exaggerately said to be 3,000 feet long.
So did Abraham Lincoln and Santa Clause.
Some people call “Soup catcher” or “Flavor Saver”.
Posted by 剛先生 at
14:48
│Comments(2)
2012年12月22日
2012年12月22日
人生2回論 5
最近は、中津校ではあまりやってませんが、
以前はバートランド・ラッセルの
幸福論をやっていました。
この本は、ものすごく楽しい本で
・・・今からおそらく7,80年も前の作品だ
と思いますが、でも、現在の問題を
うまく言い当てていることがものすごく多いのです。
その中で、「人間はある程度、
時間を割り当てられている仕事があることが、
幸せなのだ」というのです。
余程、創意工夫のできる人だったら、
1日中、決まった仕事がなくても、
自分で時間を振り当てて、
楽しく過ごすことも出来るだろうが、
普通の人だったら、1日の内、
きまりきった仕事があるほうがずっといいというのです。
まったく割り当てられる時間がなく、
1日中まったく自由に過ごしていいのだといわれると、
実際困ってしまう・・・と言うのです。
この文は、多くのことが機械化されて、
労働者に多くの自由時間が生じてきた
時代に書かれたものです。
こういった指摘は、
今や高齢化社会にあてはまる気がします。
以前はバートランド・ラッセルの
幸福論をやっていました。
この本は、ものすごく楽しい本で
・・・今からおそらく7,80年も前の作品だ
と思いますが、でも、現在の問題を
うまく言い当てていることがものすごく多いのです。
その中で、「人間はある程度、
時間を割り当てられている仕事があることが、
幸せなのだ」というのです。
余程、創意工夫のできる人だったら、
1日中、決まった仕事がなくても、
自分で時間を振り当てて、
楽しく過ごすことも出来るだろうが、
普通の人だったら、1日の内、
きまりきった仕事があるほうがずっといいというのです。
まったく割り当てられる時間がなく、
1日中まったく自由に過ごしていいのだといわれると、
実際困ってしまう・・・と言うのです。
この文は、多くのことが機械化されて、
労働者に多くの自由時間が生じてきた
時代に書かれたものです。
こういった指摘は、
今や高齢化社会にあてはまる気がします。
タグ :60歳から働く場所を2度目の人生
2012年12月22日
人生2回論 4
これは正確かどうか、確認していませんが
・・・こんな話を聞いたことがあります。
アメリカでは、ある経験豊富な看護婦さんが
・・・おそらく資格試験みたいなことは
あるのでしょうが、ある程度、
治療ができるようになっているというのです。
アメリカやオーストラリアでは、
隣村といっても、
200キロも離れているというのです。
したがって、ちょっとした病気で
何百キロも離れた町の病院に行くことも大変です。
それで、村には小さな診療所があり、
そこに看護婦さんみたいな人がいて、
その人がある程度の治療するらしいのです。
もちろん、中央の大きな病院とタイアップしていて、
コンピューターで、そこの医師と緊密に連絡をとりあって、
治療したり、その病院に送り込んだりするらしいのです。
日本でもこのような制度があるといいですね。
60歳ぐらいになったとき、
このようなチャンスがあれば、励みになります。
・・・こんな話を聞いたことがあります。
アメリカでは、ある経験豊富な看護婦さんが
・・・おそらく資格試験みたいなことは
あるのでしょうが、ある程度、
治療ができるようになっているというのです。
アメリカやオーストラリアでは、
隣村といっても、
200キロも離れているというのです。
したがって、ちょっとした病気で
何百キロも離れた町の病院に行くことも大変です。
それで、村には小さな診療所があり、
そこに看護婦さんみたいな人がいて、
その人がある程度の治療するらしいのです。
もちろん、中央の大きな病院とタイアップしていて、
コンピューターで、そこの医師と緊密に連絡をとりあって、
治療したり、その病院に送り込んだりするらしいのです。
日本でもこのような制度があるといいですね。
60歳ぐらいになったとき、
このようなチャンスがあれば、励みになります。