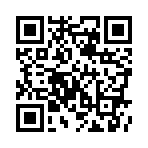2013年01月04日
ジャンクリストフ
新年おめでとう。今年もがんばるぞ。
新年に際して、あなたたちに贈りたい言葉があります。
これは、ロマン・ローランの書いた
ジャンクリストフという小説の一節です。
この小説はベートーヴェンの人生を、
そのモデルにして描いたものだといわれています。
主人公のジャンクリストフが、
人生に悲嘆して、酒ばかり飲んで、
自堕落になっていたとき、
叔父さんのゴットフリートが、
まるで歌うように彼に諭す言葉です。
「明けて来る新しい日に対して、敬虔な心をお持ち!
1年の後、10年の後、どうなっているか考えるのはやめるがいい。
今日というこの日のことを考えるがいい。
理屈はみんな、まず差し置いてしまうがいい。
いいかい、みんなだよ。馬鹿げているよ。
悪い結果を持ってくるよ。
人生に無理な力を加えてはいけないよ。
今日を生きることだよ。
その日、その日に対して敬虔でおあり。
その日、その日を愛して、尊敬して、
何よりもその日その日をしぼませないことだよ。――-」
「それだけでは少なすぎます」とクリストフは言った。
ゴットフリートは親しみ深い笑い声を立てた――
「それは誰にも出来ないほど多くのことを望むことなんだ。
お前は傲慢だね。お前は英雄になりたがっているんだ
―― 英雄とは自分のできることをする人なんだろう――」
―――
「・・・そうだ・・・とにかく・・・それだけでも十分だ」
こうしてクリストフは、
その日、その日を精一杯生きるのだと決心するのです。
明日のことなど考えずに、
その日、その日が花咲くように生きればいいのだ、
それだけで十分だと考えるのです。
本当に、その日、一日を大切に生きれば、
1年の後には、あなたたちの夢にたどり着いています。
新年に際して、あなたたちに贈りたい言葉があります。
これは、ロマン・ローランの書いた
ジャンクリストフという小説の一節です。
この小説はベートーヴェンの人生を、
そのモデルにして描いたものだといわれています。
主人公のジャンクリストフが、
人生に悲嘆して、酒ばかり飲んで、
自堕落になっていたとき、
叔父さんのゴットフリートが、
まるで歌うように彼に諭す言葉です。
「明けて来る新しい日に対して、敬虔な心をお持ち!
1年の後、10年の後、どうなっているか考えるのはやめるがいい。
今日というこの日のことを考えるがいい。
理屈はみんな、まず差し置いてしまうがいい。
いいかい、みんなだよ。馬鹿げているよ。
悪い結果を持ってくるよ。
人生に無理な力を加えてはいけないよ。
今日を生きることだよ。
その日、その日に対して敬虔でおあり。
その日、その日を愛して、尊敬して、
何よりもその日その日をしぼませないことだよ。――-」
「それだけでは少なすぎます」とクリストフは言った。
ゴットフリートは親しみ深い笑い声を立てた――
「それは誰にも出来ないほど多くのことを望むことなんだ。
お前は傲慢だね。お前は英雄になりたがっているんだ
―― 英雄とは自分のできることをする人なんだろう――」
―――
「・・・そうだ・・・とにかく・・・それだけでも十分だ」
こうしてクリストフは、
その日、その日を精一杯生きるのだと決心するのです。
明日のことなど考えずに、
その日、その日が花咲くように生きればいいのだ、
それだけで十分だと考えるのです。
本当に、その日、一日を大切に生きれば、
1年の後には、あなたたちの夢にたどり着いています。
2012年12月12日
人生2回論 1
以前は、人間の平均寿命は70歳前後でしたから、
55歳、60歳の定年で退職した場合、
10年程度で定年人生を全うする
ということが多かったのではないかと思います。
しかし、現在では、80歳までも生き、
さらに85,90歳まで生きる人が多くなっています。
もし、85歳まで生きるとしたら、
そして60歳で定年になったとしたら、
定年後の人生が、20年、25年も
あるということになります。
これは・・・どう見ても、
年金生活で過ごせる長さではありません。
この人生が楽しくなければ、
その人の人生そのものが幸せではなくなる
のではないかと思います。
とすれば・・・この25年間を、
今までのように、仕事もしないで、
年金だけで過ごすのではなく、
何かを新しく・・・いや・・・
新しくなくてもいいけど、少なくとも、
余生を平穏に生きればそれでいいというのではなく、
むしろ、この人生をもっと有意義に
生きるように考えることが、
重大になっているといえる気がします。
私は、本気でそう思っているのですが、
人生は2つに分けて生きるべきだと思うのです。
初めは、定年年齢の60歳まで、
次が60歳以後の人生です。
初めの人生は、子供を育てるなどのしがらみがあり、
ある程度妥協的な人生であるとしても、
後半の第2の人生は、自分の納得の行く
人生でありたいと思うのです。
55歳、60歳の定年で退職した場合、
10年程度で定年人生を全うする
ということが多かったのではないかと思います。
しかし、現在では、80歳までも生き、
さらに85,90歳まで生きる人が多くなっています。
もし、85歳まで生きるとしたら、
そして60歳で定年になったとしたら、
定年後の人生が、20年、25年も
あるということになります。
これは・・・どう見ても、
年金生活で過ごせる長さではありません。
この人生が楽しくなければ、
その人の人生そのものが幸せではなくなる
のではないかと思います。
とすれば・・・この25年間を、
今までのように、仕事もしないで、
年金だけで過ごすのではなく、
何かを新しく・・・いや・・・
新しくなくてもいいけど、少なくとも、
余生を平穏に生きればそれでいいというのではなく、
むしろ、この人生をもっと有意義に
生きるように考えることが、
重大になっているといえる気がします。
私は、本気でそう思っているのですが、
人生は2つに分けて生きるべきだと思うのです。
初めは、定年年齢の60歳まで、
次が60歳以後の人生です。
初めの人生は、子供を育てるなどのしがらみがあり、
ある程度妥協的な人生であるとしても、
後半の第2の人生は、自分の納得の行く
人生でありたいと思うのです。
2012年10月28日
みんなのまとめ役はゴッド
今年の生徒の中にゴッドと呼ばれている
浪人生がいます。彼は、一度目の浪人中に
腰を痛めて入院、今回は2浪目なので、
みんなより年上です。
彼には独特の余裕があって、みんなを和ませ、
彼の周りは笑いが絶えません。
しかし、彼は今回、大分から中津へ覚悟して
浪人をしに来ているのです。
余裕を見せていますが、実は後がないぞという
必死な気持ちで、この一年をがんばっているのだと思います。
先日の映画の鑑賞会も、初めは皆と一緒に見ていたのですが、
いつの間にか、自習室に戻って勉強していました。
やはり、こんな時間はないという緊張感を常に持っている
証拠かなと思い、改めて見直しました。
彼は生徒のまとめ役として、私たちも多いに頼りにしています。
穏やかで、人と争わず、かといって、自分をきちんと持っている
ゴッド君が、目指す大学に通る努力をしてゆくように
見守っています。
彼は、今夜も、他の生徒が帰った後、一緒に戸締りをして
単車で、下宿に帰って行きました。
浪人生がいます。彼は、一度目の浪人中に
腰を痛めて入院、今回は2浪目なので、
みんなより年上です。
彼には独特の余裕があって、みんなを和ませ、
彼の周りは笑いが絶えません。
しかし、彼は今回、大分から中津へ覚悟して
浪人をしに来ているのです。
余裕を見せていますが、実は後がないぞという
必死な気持ちで、この一年をがんばっているのだと思います。
先日の映画の鑑賞会も、初めは皆と一緒に見ていたのですが、
いつの間にか、自習室に戻って勉強していました。
やはり、こんな時間はないという緊張感を常に持っている
証拠かなと思い、改めて見直しました。
彼は生徒のまとめ役として、私たちも多いに頼りにしています。
穏やかで、人と争わず、かといって、自分をきちんと持っている
ゴッド君が、目指す大学に通る努力をしてゆくように
見守っています。
彼は、今夜も、他の生徒が帰った後、一緒に戸締りをして
単車で、下宿に帰って行きました。
2012年09月14日
賢く生きる ⑤ 大黒屋光太夫
ペテルブルグの宮廷で、女帝は、彼らの苦難に
深く同情し、手厚くもてなしてくれました。
特に、光太夫が、当時の有名な学者であり
軍人でもあった、キリロ・ラックスマンと親交を
えたことが、この成功に深く関係していました。
一介の漂流者であった光太夫の人柄が、高名な
学者であるラックスマンの心を動かし、自分の
職務上出来る限りのことをして、援助を惜しま
なかったのでした。この話を読むと、その人間
としての価値が言葉を超えて伝わるのだという
ことを感じます。ラックスマンも立派な人だった
と思います。そしてまた、日本人たちも、
特に、光太夫の人柄が、この困難な旅に打ち克ち、
最後まで、帰国の希望を捨てずに努力し、帰国を
果たした大きな力となったのでした。
私たちのロシア人に対するイメージを変えて
くれる話でもあると思うのですがいかがですか。
深く同情し、手厚くもてなしてくれました。
特に、光太夫が、当時の有名な学者であり
軍人でもあった、キリロ・ラックスマンと親交を
えたことが、この成功に深く関係していました。
一介の漂流者であった光太夫の人柄が、高名な
学者であるラックスマンの心を動かし、自分の
職務上出来る限りのことをして、援助を惜しま
なかったのでした。この話を読むと、その人間
としての価値が言葉を超えて伝わるのだという
ことを感じます。ラックスマンも立派な人だった
と思います。そしてまた、日本人たちも、
特に、光太夫の人柄が、この困難な旅に打ち克ち、
最後まで、帰国の希望を捨てずに努力し、帰国を
果たした大きな力となったのでした。
私たちのロシア人に対するイメージを変えて
くれる話でもあると思うのですがいかがですか。
2012年09月14日
賢く生きる ④ 大黒屋光太夫
地図を広げてみると、北海道のはるか上にある
カムチャッカ半島から、オホーツク海を渡り、
オホーツク、ヤク-ツクを経由して、イルクーツク
モスクワを通って、ペテルブルグまでの距離を
見ると、地上の最大の大陸であるユーラシア大陸
を大きく横断しています。光太夫たちは、馬車で
この道を往復して、日本に帰国したのでした。
その寒さは、暖かい日本で育った人間には、
想像もつかないほどのものでした。
衣類をいくら重ねても、その寒さを防ぐことが
出来ず、布団のようなものに包まっても、中の
人間は、凍傷を起こすほどでした。
仲間の一人はそれが元で、片足を切らなければ
なりませんでした。光太夫たちが広いロシアの
平原を旅していたとき、高い木の上に、ぶら下が
った馬の死骸をたくさん見ました。現地の人の
話では寒さで、死んだ馬たちが、雪の中でそのまま
放置され、春になると、木の枝にひっかかった
状態で、高い木々の上に残るのだそうです。
それほどの寒さであり、雪の深さでもあった
のです。
彼らは、思いがけず、ロシア人の親切に助けら
れて、この大旅行をやり遂げ、都のペテルブルグ
へ着きました。宮廷で、当時の女帝エカテリーナ
女王に謁見を許されました。そして、とうとう、
日本に帰る許可をもらったのでした。
その話は次で。(つづく)
カムチャッカ半島から、オホーツク海を渡り、
オホーツク、ヤク-ツクを経由して、イルクーツク
モスクワを通って、ペテルブルグまでの距離を
見ると、地上の最大の大陸であるユーラシア大陸
を大きく横断しています。光太夫たちは、馬車で
この道を往復して、日本に帰国したのでした。
その寒さは、暖かい日本で育った人間には、
想像もつかないほどのものでした。
衣類をいくら重ねても、その寒さを防ぐことが
出来ず、布団のようなものに包まっても、中の
人間は、凍傷を起こすほどでした。
仲間の一人はそれが元で、片足を切らなければ
なりませんでした。光太夫たちが広いロシアの
平原を旅していたとき、高い木の上に、ぶら下が
った馬の死骸をたくさん見ました。現地の人の
話では寒さで、死んだ馬たちが、雪の中でそのまま
放置され、春になると、木の枝にひっかかった
状態で、高い木々の上に残るのだそうです。
それほどの寒さであり、雪の深さでもあった
のです。
彼らは、思いがけず、ロシア人の親切に助けら
れて、この大旅行をやり遂げ、都のペテルブルグ
へ着きました。宮廷で、当時の女帝エカテリーナ
女王に謁見を許されました。そして、とうとう、
日本に帰る許可をもらったのでした。
その話は次で。(つづく)
2012年09月13日
賢く生きる ③ 大黒屋光太夫
大黒屋光太夫 -2
光太夫たちが漂着した島にいたロシア人
たちは、口々に光太夫たちに話しかける
のですが、全く何を言っているのかわか
りません。
彼らは、光太夫たちの持ち物を指差して、
しきりに「エトチョワ」と言います。
光太夫は考えて、同じ言葉を身近な
鍋を指して、ロシア人に発してみました。
すると、彼らがうれしそうに、それを指
してロシア語で「。。。。」といいます。
光太夫は「ははあ、エトチョワとは、これは
何ですか、と言う意味なのではないか。すると、
鍋はロシア語では。。。というのか」と推測して、
次々に、別のものを指差しては「エトチョワ」と
言ってみました。
ロシア人たちは、得意そうに次々と答えて
くれます。几帳面な光太夫は、それらを
書き留めて、仲間にも教え、彼らは、
簡単なロシア語を学んでいったのです。
島にいるロシア人の保護の下、光太夫
たちは何とか、そこで、4年間を生き
延びました。 (つづく)
光太夫たちが漂着した島にいたロシア人
たちは、口々に光太夫たちに話しかける
のですが、全く何を言っているのかわか
りません。
彼らは、光太夫たちの持ち物を指差して、
しきりに「エトチョワ」と言います。
光太夫は考えて、同じ言葉を身近な
鍋を指して、ロシア人に発してみました。
すると、彼らがうれしそうに、それを指
してロシア語で「。。。。」といいます。
光太夫は「ははあ、エトチョワとは、これは
何ですか、と言う意味なのではないか。すると、
鍋はロシア語では。。。というのか」と推測して、
次々に、別のものを指差しては「エトチョワ」と
言ってみました。
ロシア人たちは、得意そうに次々と答えて
くれます。几帳面な光太夫は、それらを
書き留めて、仲間にも教え、彼らは、
簡単なロシア語を学んでいったのです。
島にいるロシア人の保護の下、光太夫
たちは何とか、そこで、4年間を生き
延びました。 (つづく)
2012年09月12日
賢く生きる ② 大黒屋光太夫
大黒屋光太夫といっても、日本史に詳しい人
にしか知られていないかもしれません。
江戸幕府の鎖国時代に、伊勢半島から船出して、
ひどい嵐に会い、7ヶ月も太平洋を漂流して、
カムチャッカ半島から、何百キロも離れた、
孤島に漂着、ロシア人の好意で、あの広大な
シベリアの平原を往復して、10年の歳月をかけて、
日本に帰国しました。日本に帰りついたのは初め
17名だった乗組員のうちたった2名だけでした。
光太夫とその乗組員の苦難の旅は、私たちの想像
をはるかに超えるものでした。まず、言葉が全く
わからない、その上、寒さが言葉に出来ないほど
厳しく、仲間の中には、凍傷で足を切り落とさ
なくてはならなくなった人もいました。
彼が、無事に生きて帰国することが出来たのは
本当に奇跡的なことでした。
でも、光太夫の知恵と人間性もまた、この奇跡を
成せた大きな要因であったのです。(つづく)
にしか知られていないかもしれません。
江戸幕府の鎖国時代に、伊勢半島から船出して、
ひどい嵐に会い、7ヶ月も太平洋を漂流して、
カムチャッカ半島から、何百キロも離れた、
孤島に漂着、ロシア人の好意で、あの広大な
シベリアの平原を往復して、10年の歳月をかけて、
日本に帰国しました。日本に帰りついたのは初め
17名だった乗組員のうちたった2名だけでした。
光太夫とその乗組員の苦難の旅は、私たちの想像
をはるかに超えるものでした。まず、言葉が全く
わからない、その上、寒さが言葉に出来ないほど
厳しく、仲間の中には、凍傷で足を切り落とさ
なくてはならなくなった人もいました。
彼が、無事に生きて帰国することが出来たのは
本当に奇跡的なことでした。
でも、光太夫の知恵と人間性もまた、この奇跡を
成せた大きな要因であったのです。(つづく)
2012年09月10日
賢く生きる ① 石田三成
石田三成の賢さ
ある日、秀吉は馬の遠乗りに出かけました。
暑い日で、秀吉はかなり疲れて喉も渇いて
いました。、それで、最寄の寺へ入り、
休憩することにしたのです。
喉がひどく渇いていたので、茶を所望
しました。
寺の見習い小僧が、秀吉のためにお茶を
給仕しました。ひどく喉が渇いていた秀吉は
一気に一杯目を飲み干しました。
そして、もう一杯と小僧に言いました。
小僧は、二杯目を持ってきました。
そのお茶は、さっきのお茶より少し熱く
してありました。それも飲み干した秀吉は
三度目を命じたのです。小僧が持って
きたお茶は熱く濃く入れてありました。
秀吉は、全てのお茶を飲んだ後、
小僧に聞きました。
「なぜ、初めのお茶はぬるかったのか」と。
すると、その小僧は、「喉が渇いているときに
は、たくさん飲みたいものです。だから、
殿が飲みやすいようにと、ぬるめに立てました」
と答えたのです。その子の名を聞くと、秀吉は
すぐに、「わしの家来にならないか」と
言って、つれて帰ったと言うことです。
この小僧が、後に秀吉の一番の知恵袋と
呼ばれた、石田三成です。
心を配ると言うことは、相手の身になって
考えると言うことです。
ある日、秀吉は馬の遠乗りに出かけました。
暑い日で、秀吉はかなり疲れて喉も渇いて
いました。、それで、最寄の寺へ入り、
休憩することにしたのです。
喉がひどく渇いていたので、茶を所望
しました。
寺の見習い小僧が、秀吉のためにお茶を
給仕しました。ひどく喉が渇いていた秀吉は
一気に一杯目を飲み干しました。
そして、もう一杯と小僧に言いました。
小僧は、二杯目を持ってきました。
そのお茶は、さっきのお茶より少し熱く
してありました。それも飲み干した秀吉は
三度目を命じたのです。小僧が持って
きたお茶は熱く濃く入れてありました。
秀吉は、全てのお茶を飲んだ後、
小僧に聞きました。
「なぜ、初めのお茶はぬるかったのか」と。
すると、その小僧は、「喉が渇いているときに
は、たくさん飲みたいものです。だから、
殿が飲みやすいようにと、ぬるめに立てました」
と答えたのです。その子の名を聞くと、秀吉は
すぐに、「わしの家来にならないか」と
言って、つれて帰ったと言うことです。
この小僧が、後に秀吉の一番の知恵袋と
呼ばれた、石田三成です。
心を配ると言うことは、相手の身になって
考えると言うことです。